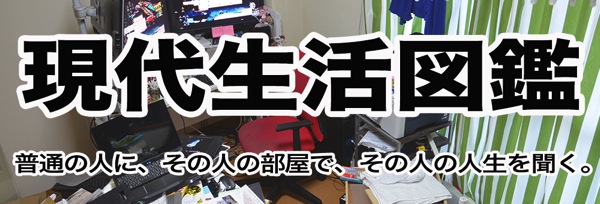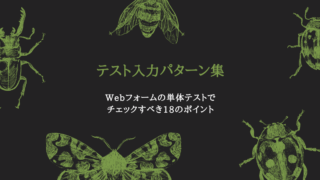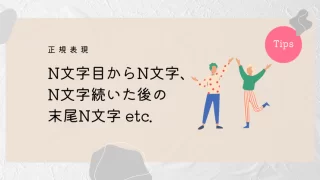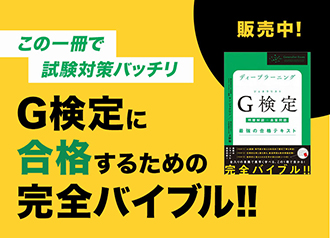前回、アメリカのバレンタインデーがいかに色んな業界・業種(特に推定1,400万人のプロポーズする・される人とそれに絡む商売)にとって稼ぎ時か、というお話をした。

実は私もそんな推定1,400万人のひとりで、ダイヤの指輪をいただいてしまったのだ。バレンタイン前日である13日の金曜日の夜、原稿締め切り間際なのにネタがひとつも思い浮かばぬままバレンタインの夕飯などに出かけるハメとなり、そしたら「今日はスペシャル・ギフトを用意したよ」とかいって彼氏がティファニーの箱をよこしてきたわけだ。それから派生して前回のネタへ辿り着くことと相成ったわけだ。
で、なんでこんな屁のツッパリにもならない裏話を持ち出したかというと、私が13日の金曜日に婚約するとかいう相変わらずオモロイ女アピールをするためではない。彼(婚約者と呼ぶべき?)がティファニーで指輪を買うに至った決め手がなかなか面白かったからだ。
普通、指輪でも何でも、何かモノを買うときの判断材料って、価格・品質・機能・デザイン・耐久性・ブランドイメージとか、その辺がモノ自体を選ぶときの常習な判断基準だろう。あとは小売店のサービスとか接客とか、モノ自体ではなく売ってる店を選ぶ際の基準もあるが、ま、このあたりが概ねの相場かと思う。
ところが彼がティファニーで買うことにした一番の決め手は、これらのどれでも無かったのだ。色々調べた結果ティファニーは、貴金属やダイヤモンドの鉱山労働者を搾取してなさそうだという人権侵害とは無関係なこと、環境汚染にもきちんと配慮した採掘活動をしていること、世界の紛争地域が反政府活動の資金調達に使うために流通させるいわゆる”紛争ダイヤモンド”とは無関係であることなど、一言でいうならば「フェアトレード」を忠実に実行していることがティファニーを選んだ決め手だというのだ。
私の友人でもティファニーだのカルティエだのヴィトンだのブランド指輪・小物を持ってる女性が何人もいるが、
「このヴィトンの財布ー、フェアトレードだからー、好きなのぉー」
「このカルティエの時計さー、フェアトレードだからー、旦那にー、オネダリしちゃったー」
「結婚指輪はー、フェアトレードが良かったからー、ティファニーに決めたのぉー」
なんて発言を誰一人からも聞いたことがない。なので彼がティファニーで購入することに決めた一番の理由というのが、なかなか面白いなと思ったのだ。
こんな風に、自分の価値観・倫理観にあったモノを買い求める、というか、自分の価値観・倫理観に合わないモノの買い物は避けたいという動きが今、アメリカでは台頭している。
おそらく発端は、俗に言う「ミレニアル世代(Millennials Generation)」なる1980年代から200年代初頭あたりに生まれた世代の消費パターンから来ているのだと思われる。情報もモノもあふれるくらい豊かな世の中で生まれ育ったこの世代の消費傾向として、オリジナルなもの、価値の見出せるもの、信頼・共感できるものだったら、ちょっと高くても買うというがある。
なので彼らからしてみれば、何かモノを買うときに、値段・品質・機能・デザインといった従来の購買基準を加味するのは当たり前な前提で、そのうえ価値観や共感度を測れるようなモノサシも使わないことには決め手に欠ける、という感覚なのかもしれない。
もちろんミレニアル世代が購買力を得る何年も前から、価値観に重きを置いた購買判断をする人もいただろうが、一部すぎてメインストリームにならずにいたのだろう。たとえばゲイの人であれば同性愛を支持できない売り手からは買いたいと思えないとか、有機栽培のモノ以外は地球に優しくないと信じる人はオーガニックのモノしか買いたくないなど。そういった一部の価値観ベースの購買判断を下してきた人たちに、ミレニアル世代が大人となり大きな購買力となったことで、やっとこんな買い物の仕方も新勢力として台頭してきた……という感じだろう。
約一年前に取り上げた、飲食品のNon-GMO(遺伝子組み換え作物未使用)表記なんかがこの好例だ。人によっては、遺伝子を組み換えたモノなど口に入れたくないという価値観もあるし、遺伝子組み換えまでして大量生産・販売しようとする企業理念に共感できないという倫理観もある。そんな人たちにとってNon-GMO表記は、価値観・倫理観の判断材料として機能するわけだ。

また最近登場したアプリ「Glia」は、まさにこういった価値観・倫理観ベースの購買判断サポートをしてくれる。数十個ある価値観リストから自分が支持する理念・信念を5個以上選んで、自分の価値観プロファイルを事前登録する。


そうすると、たとえば昼食にサンドイッチ屋に行きたいなとなったとき、近所のサンドイッチ屋のなかでどこが一番自分の価値観に近いか、または外れてる店かという価値観マッチング度合いが地図上に店名とともに表示される。よって、「地産地消の推進、同姓婚の容認、銃規制を支持しているサンドイッチ屋は近くにあるかな?」などという、従来では全く考えられなかったような買い物の選択が可能になる。
ほかにも最近登場したアプリ「Buy Partisan」は、モノの製造元企業がどの政党に傾倒してるかを教えてくれる。商品のバーコードをこのアプリでスキャンすると、その製造元企業と企業幹部がどの政党にいくら献金してるかなどが分かるという仕組み。これにより、「オレは共和党への忠誠心が強いから、民主党にばっかり献金してるような会社の作ったモノは買わないぜ」という購買判断もできるようになる。
言い換えるならば、従来のように品質・味・機能・デザイン・値段がバチっと合った売れそうなモノを作っても、売り手の価値観・倫理感が消費者のそれと合ってないとモノが売れなくなる世の中がやってくるかもしれないということだ。
ヘンな話、数年後には私の女友達も
「ダイヤモンドの指輪ってー、ダイヤの透明度とかも重要だけどー、やっぱフェアトレードなのが一番好きー」
とか言い始める可能性もアリだし、日本の女性ファッション誌の表紙に
『いつもの服にさりげなく……いい女はフェアトレード・ジュエリーを選んでいる!』
とかいう謳い文句が踊り始める可能性もアリ、だ。
参考資料
以前紹介したミレニアム世代の記事はこちら。