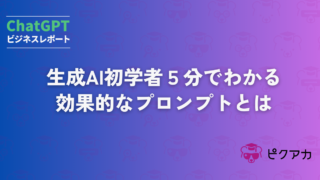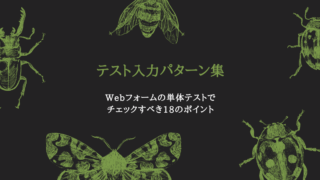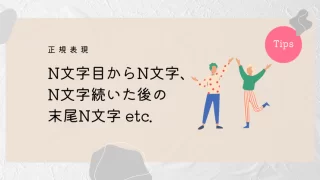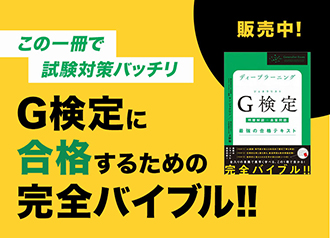サンプリング定理の明かりにくい応用例を1つ噛み砕いて解説させていただきたいと思います。今回の話題は弊執のデータサイエンティスト検定(DS検定)のテキストをお読みになり、その上でとても素晴らしい質問をしてくださった読者様に感謝いたします。
初めに、サンプリング定理とは以下のようなことを言っています。
A-D 変換でデジタル信号に正確に変換するためには、再現したい信号に含まれ る最も高い周波数の 2 倍を超えるサンプリング周波数で標本化を行う必要があります。
これを満たせば、デジタル化された後のデータから元のアナログ信号の波形を正確に再現できます。 上記を言い換えると、サンプリング周波数の半分の周波数までの信号は再現可能で す。この限界をナイキスト周波数と呼びます。
以下は弊執の データサイエンティスト検定(DS検定)のテキスト のpg318に掲載された演習問題の1つです。

本書に掲載された解説も提示します。

読者様の疑問
これに対して、読者様からいただいた疑問は以下の通りである、
318頁の最終行で、「24kHz以上」は「24kHz以下」、「上限が小さい」は「上限が大きい」の間違いではないでしょうか。
最終行を再び書き出します:
D-A変換によりデジタルデータを音に復元する際、スピーカーやヘッドホンなどの周波数帯域が不十分であると、データの情報が十分に復元されません。保存されたデータが48kHzであれば、復元可能な範囲で最大限復元するには、周波数帯域の上限が24kHz以上のスピーカーを用いる必要があリます。それよりも上限が小さいスピーカーでは、高音領域が復元できません。
これは選択肢3(文章は以下)への解説である。
この音声データの情報を、復元可能な範囲で最大限復元するには、周波数帯域の上限が48kHz以下のスピーカーを用いる必要がある。