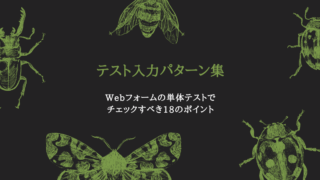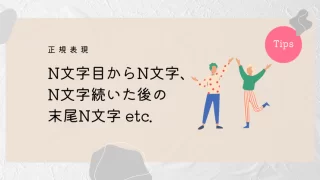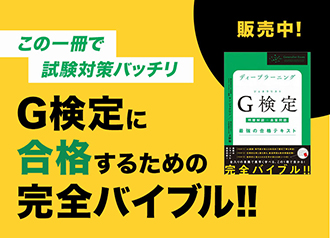本記事の背景
Generative AI(生成AI)が急速な進化し、幅広い産業で導入されていく中で、コンテンツ生成や意思決定プロセスに生成AIを統合する企業が続出しています。そこで、生成AIがビジネス、イノベーション、市場構造、戦略に与える影響を包括的に理解することが重要になってきています。
ところで、これまで見てきた研究報告や論文では、生成AIのアルゴリズム的進化や特定のアプリケーションに関する技術的側面に焦点を当てているものが多く、経済、組織、社会に与える影響を十分に考察できているとは言えません。例えば、コンテンツの自動生成に関する研究は、その効率性や各業界への影響を詳しく調査されているものの、ビジネスモデル革新の戦略には十分に触れられていません。また、生成AIの倫理的活用や規制の必要性に関する議論は、持続可能なビジネスの視点から十分に議論されていません。
そこで、今回は生成AIのビジネスと社会への影響を評価した、以下の文献を内容の中から、上記に寄与する部分を体系的にまとめました。
Transforming Business with Generative AI: Research, Innovation, Market Deployment and Future Shifts in Business Models
(*) 論文リンク:https://arxiv.org/pdf/2411.14437
文献(*)のねらいは、生成AIが従来のビジネスモデルの再構築、市場競争の変革や激化、イノベーションの促進において果たしている役割について明確にすることです。そうすることで、ビジネスリーダー、政策立案者、研究者にとって有益な知見を提供し、生成AIの戦略的かつ責任ある活用の指針を示唆することを目指しています。
実際、文献(*)は非常に広範囲のトピックをカバーしており、この記事では「AI TRiSM」(こちらの記事を参照)に直接関係する要素を中心にまとめていきます。
生成AI(生成AI)がもたらす影響とリスク
生成AIは、業務の効率化、意思決定の高度化、新しいビジネスモデルの創出を促進し、今後の経済発展の中心的な存在になる可能性があります。しかし、プライバシーの侵害、誤情報の拡散、自律システムの悪用といった深刻なリスクももたらしています。
生成AIの可能性を最大限に活かしつつ、リスクを最小化する責任あるAIの活用には、規制の整備、知的財産権の整理、雇用への影響への対応、情報の正確性確保、AIの安全性確保、人間とAIの協力、持続可能性、教育支援、国際的な協力体制をカバーする包含的な枠組みと対応が必要です。
■知的財産権と法的課題
生成AIの生成コンテンツに関する著作権や所有権に関する法律やルールの整備が現時点で不十分です。そのため、著作権や所有権が不明確な場合があります。これは生成AIをビジネスに使用する企業にとってリスクとなります。例えば、AI生成コンテンツが他者の著作物と類似する場合、法的紛争に発展する可能性があります。
以下の内容を、ディープラーニングG検定(ジェネラリスト)最強の合格テキスト[第2版]から引用します。
例えば、OpenAI社の規約によると、ChatGPTの生成物の著作権は基本的にユーザーに帰属するとされているが、これは決して他者の著作権を侵害していないことを保証しているわけではありません。生成AIを用いた生成物が他者の著作物と類似し、かつ作成において他者の著作物に依拠している場合、著作権法に違反する可能性があります。しかも、この「依拠しているかどうか」の判断は容易ではありません。「生成 AI の利用者がその著作物を認識していたか」、「その生成AI の学習に当該著作物が用いられていたかどうか」などが考慮 されると考えられています。なお、AIの学習に著作物を無断で使える特例(著作権法の第30条の4第2号)があるものの、生成プロセスの場合、他人の著作物を入力し、 他人の著作物に依拠した生成物を出力される場合には特例は適用されず、複製・翻案に該当します。
■雇用への影響と社会的課題
生成AIの普及は、業務の効率化を促進する一方で、特定の職種における雇用喪失を引き起こす可能性があります。最も喪失しやすい職業はデータ入力、翻訳、カスタマーサポート業務といった「単純作業」や「繰り返し作業」に該当するものです。これはAIの得意な領域であるためです。他方で、デザイナーやライターといった「クリエイティブ職」では、AIとの共存が求められます。職業が喪失するだけではなく、新しい職業が生まれます。AIの運用や管理に特化した職種の需要が増加することが期待されています。
以上により、企業はAIと人間が共存できる環境を整え、従業員のスキルアップを支援する必要があります。
■偏見・誤情報の拡散リスク
AIはその学習に使用されたデータに依存します。そのデータには人間社会の偏見や誤った情報を含む可能性が当然あるため、学習済みのAIは既存の偏見を強化したり、不正確な情報を生成するリスクがあります。以下の項目は代表的なリスクの種別です。
- AIのバイアス:訓練データに含まれる人種・性別・文化的偏見がAIの出力に反映される可能性がある。
- 誤情報の拡散:信頼性の低い情報を大量生成し、社会に混乱を招く危険性がある。
- 透明性の欠如:AIの意思決定プロセスが「ブラックボックス化」し、判断根拠が不明確になるため、AIの信頼性が下がる。
■AIの暴走リスク
AIが高度に自律化し、人間の制御を超えてしまうリスクも議論されています。AIが自己学習や自己進化を繰り返すことにより、人間の意図しない行動を取る可能性が出てきます。この場合、サイバー攻撃、フェイクニュース生成、自律型兵器などに利用された場合の被害が深刻化します。
AIの自律性の研究を一方的に止めることができないが、AIの制御と安全性を確保するためには、厳格なルール策定と継続的な監視、国際的な規制が不可欠です。
■規制と倫理的監視
生成AIの活用に関する規制は、データのプライバシー、透明性、責任、そして差別的な結果を招く可能性のあるアルゴリズムの偏りを軽減することに重点を置くべきと指摘されています。AI規制の先駆者であるEUのAI Act法は、リスクレベルに応じてAIシステムを分類し、それぞれのカテゴリーに対してターゲットを絞った要件を導入しています。
また、AIの規制が国ごとに異なると、技術の発展において「AIナショナリズム(国ごとの独自規制による技術の囲い込み)」が生じてしまい、国際的な協力が難しくなる恐れがあります。そのため、国境を越えた倫理的なガイドラインを策定し、グローバルな視点でAIの活用を進めることが重要とされています。
■人間とAIの協力モデル
ビジネスにAIを統合するためには、「人間とAIの協力モデル」を慎重に考慮すべきです。効果的な「人間とAIの協力モデル」は、AIを人間の専門知識を補完するものとして位置付け、置き換えるものではないとしています。つまり「人間の関与」は重要であり、特に医療や金融のような高リスクの産業において透明性と責任を維持するために必須です。例えば、診断放射線学では、AIは膨大なデータパターンを分析することで人間の意思決定を補強できますが、放射線科医は正確な診断に必要な文脈的な専門知識を提供します(Topol, 2019)。AIが反復的またはデータ集約的なタスクを支援する能力が高く、これを人間の知恵と直感と組み合わせるような仕組みを作ることによって、バランスの取れた人間とAIの共生的な関係を育むことができます。
■AI駆動の世界におけるスキル開発と教育
AIの進展に伴い、AIと協働する未来の労働力を支えるためのスキルの獲得が重要となります。学校教育及び職場における「教育」や「研修」は、テクノロジーそのものに関すSTEM(科学・技術・工学・数学)だけではなく、人文学、倫理、創造性、想像力(HECI)を組み込んだプログラム、そして問題解決能力や適応力、倫理的な判断力などの「ソフトスキル」の強化もを取り入れる必要があります。
AIの発展に伴い、一般の人々がその仕組みや限界、倫理的課題を正しく理解することも求められます。AIに関する知識が不足すると、不安や誤解が広がり、不適切な利用につながる恐れがあります。そのため、AIの基本概念を普及させるための教育キャンペーンや無料の学習リソースがより多くの人々に提供されるべきと考えられています。
■AIにおけるグローバルな視点と包括性
生成AIのグローバルな影響力の拡大に伴い、AI開発の公平性と包括性の確保が重要な課題となっています。国や地域によってAIへのアクセス、教育、リソースの格差が大きく異なり、この格差が社会経済的不平等をさらに広げる可能性があります。AIの持続的な発展のためにも、先進技術を持つ国々だけがAI技術の開発と利用を独占し、一部の社会階級にいる人々のみがAIの恩恵を享受する状況を防ぐために、国際的な協力が不可欠です。
また、AIそのものの公平性を高めるためには、開発プロセスに多様なバックグラウンドを持つ人々を積極的に参加させることが求められます。例えば、特定の人種やジェンダーに不利なバイアスを防ぐため、システム設計に少数派グループの視点を取り入れるべきです。
■ 持続可能性と環境への責任
技術の進歩と持続可能性の両立を目指す上で、生成AIが環境に与える影響、特にエネルギー消費の増大は、今後の重要な課題の一つです。大規模なAIモデルを動かすには膨大な計算能力が必要であり、それに伴う二酸化炭素排出量の増加が懸念されています。この問題を解決するためには、エネルギー効率の高いAIアーキテクチャの開発や、データセンターを再生可能エネルギーで運用する取り組み、AIのエネルギー消費を抑える業界標準の策定などが求められます。例えば、GoogleのBERTやAppleの小型言語モデルなど、計算資源の少ない環境でも動作可能なAIモデルの開発が進められています(Patterson et al., 2021)。
執筆担当者:ヤン ジャクリン (GRI分析官・講師)