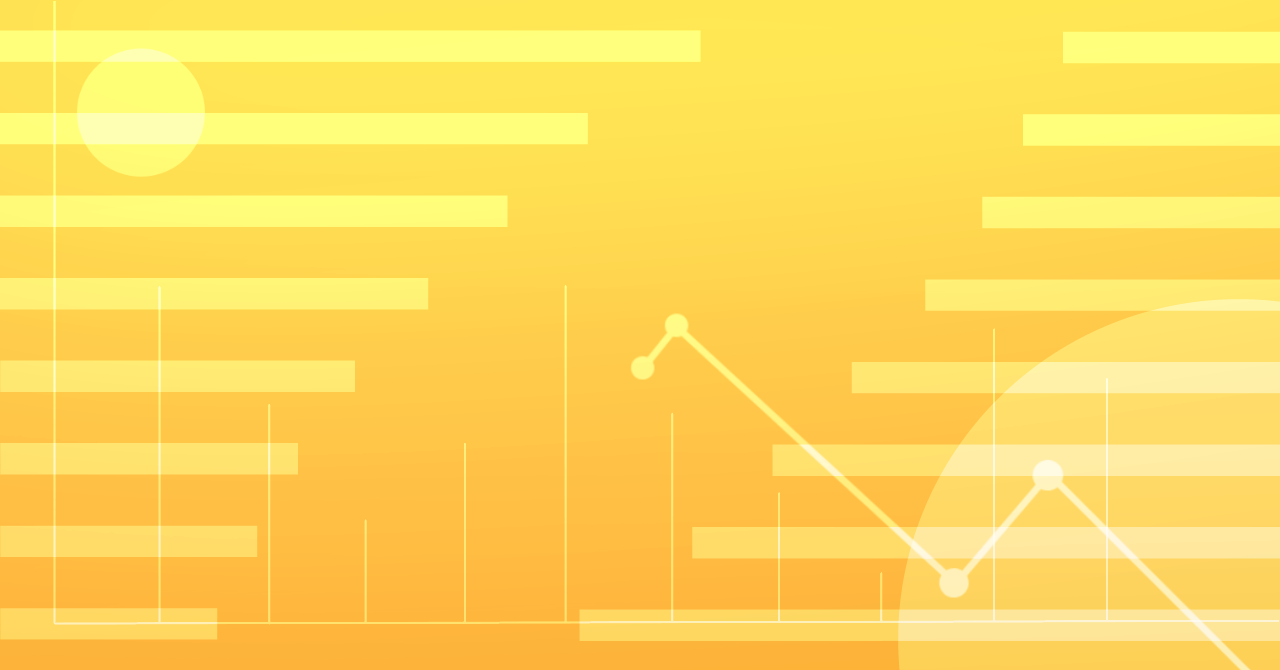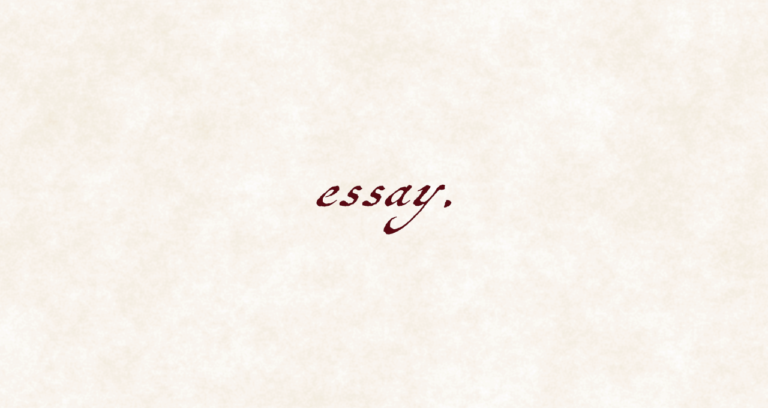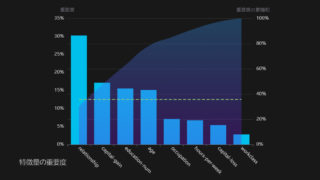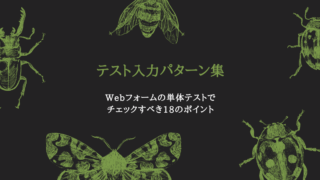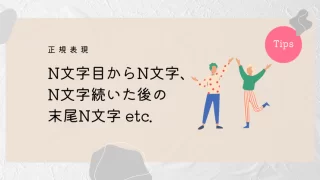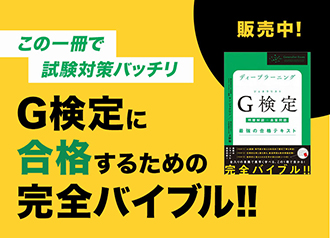テレビ局は日夜視聴率競争にさらされていることは周知の事実で、中で働いていると常に実感しているものです。これは視聴率がテレビの広告価値を示すもので、一般企業において売り上げの上下がそのまま業績に反映するところが、視聴率が媒介となって広告の売り上げを決めていくいわば通貨のようなものだからです。
その視聴率は、2000年以降ビデオリサーチ社(以下VR)1社が担うところとなり、テレビ・新聞をはじめインターネットでもその数字が見かけられ、視聴者の中には好きな番組の視聴率に一喜一憂している人もいるようです。
これを読んでいるあなたは、視聴率調査の詳細をどの程度ご存知でしょうか?実は、VR社はその調査方法についてかなりくわしくホームページで公開しています。

現在の調査方法となって20年弱が経過していますが、その価値は変わらず存在しています。いくつかその要因はありますが、そのひとつに視聴率が「意識調査=アンケートではなく視聴ログデータである」ことが挙げられます。
日頃、視聴率では分からない視聴者=消費者のインサイトを探るべく意識調査も行ってきましたが、そこでの番組視聴の状況はしばしば視聴率と違った結果となります。これは、意識での視聴行動と実際の行動に違いが見られる証で、人気番組などは実際そんなに見ていなくても後から考えればよく見たことになっている、など人間の持つ様々な情報が調査回答時に「邪魔をする」ためとも言えます。視聴者の本当の姿を知る上で視聴ログを集めているというのはとても大事なことなのです。
その一方で、最近はテレビだけをじっと見るという行動はむしろまれで、何かをしながら見る「ながら視聴」という言葉が一般化してきました。そして21世紀になってからの「ながら視聴」というのは、テレビと同時にパソコン、携帯電話に触れているものになってきました。またそれぞれの画面で見るコンテンツにも違いがあります。テレビ視聴率の調査では新しく出てきたメディアの使用状況は網羅していませんでしたが、ある調査会社がテレビもネットもスマホも、とすべてのメディア接触状況を詳らかにする仕組みをスタートさせています。
インテージ社「i-SSP(インテージシングルソースパネル)」
・同一個人からPC・モバイル・テレビなどのメディア接触データと購買データを収集
→マーケティングのひとつの流れである「シングルソースマーケティング」に マッチ
・ログデータ形式(機械式)でデータ収集→正確かつ詳細な事実に基づく分析が可能
→すべて意識調査ではなく行動調査で、消費者のありのままの姿を明らかに
・同一個人から恒常的にデータを取得しているので時間軸を踏まえた分析が可能
→ニッチな属性の細かいメディア接触動向や態度変容をつかめる
・デモグラフィック・サイコグラフィック属性など豊富な属性を保有
→意識調査とも組み合わせて「行動の裏付け」も可能に
「視聴ログ」の部分はおおよそVR社に近い調査方法で、これにパソコン・スマートフォンの接触ログが加わっているイメージです。視聴者がいつどんなテレビ番組を見て、パソコン・スマートフォンをいつ開いているかを一気に把握できることになります。テレビ局側からすれば、「ながら視聴」がいつ誰になされているかなど、具体的な視聴者像をデータから考えることができる点がメリットとなります。インターネットでどんなサイトが同時に見られているかまでわかれば、どんな番組がインターネットと連動しマルチスクリーン展開に向いているかの目安にもなるでしょう。
テレビ局がそもそも当てにしてきた視聴ログデータを包含するシングルソースデータが出回っているなら、なぜテレビ局がそれを指標にしないのか?という疑問がわいてくるかと思います。ひとつの大きな問題として、上記パネルの調査対象がインターネット利用者から行われている点があります。つまり、高齢層を中心として上記データでは日本の家族構成・人口構成を忠実に反映しきれていないのがネックだと考えられます。これまでの視聴率と意味が変わってしまう変化は歓迎されないおそれがあります。とは言え、テレビCMを流している企業の中には、上記調査の対象がターゲットに合致していて、そのデータをそのまま詳細に活用しているところもあるようです。
大勢からひとつの回答を得ることとは逆行して、1人の対象からたくさんの知見を得る「シングルソースマーケティング」はマーケティングの世界で今が旬の手法となっています。既存の視聴率に置き換わるかは別として、テレビの見方から発展して人々の生活のあり方を明らかにし、より面白くする調査でありデータになっていくことは間違いありません。