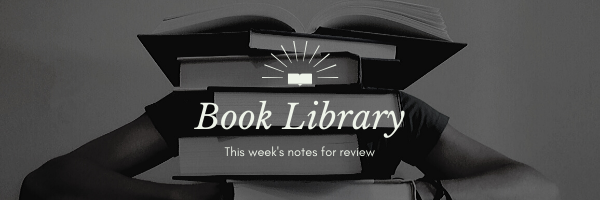REPORT
“創造的な”エンジニアの人材育成論(前編)

企業の人材育成でいま何が起きているか?
ITエンジニアリングという仕事が発生して以来抱えている企業における組織的問題(技術的負債。経営との不和。プロジェクトの理不尽。上がらない生産性。)の多くは、その仕事の不確実性への向き合い方次第だと思われる。
それら不確実性(目まぐるしい技術力の発展、新規性の高いプロジェクト、技術的課題のブラックボックス、気まぐれに移り変わる顧客市場)は、ますます予見ができない速さで大きくなり、我々の組織的課題は減るどころか増える方向に寄与していると言えよう。
我々の試みは、既存のITエンジニアとは異なる、”創造的な”エンジニアと呼ばれる技術者を想定し、どうやって育成するかという問いに答えようとするものである。
創造的なエンジニアの範疇に入るデータサイエンティストやAI開発エンジニアは、これまでのITエンジニアとは異なる。何が決定的に違うかと言うと、予め決められた設計書と完璧にwork(機能)するような完成図はそこにはない。プロジェクトにおける進め方の計画と完成予想図はあっても、プロジェクトはその通りに進まない前提でいるのだ。
わかりやすく伝えるために例えるなら、皆さんは歴史的大聖堂の建造を思い起こして頂きたい。
従来のITエンジニアが進める仕事は、「いつまでに土台を作り」「いつまでに柱を建て」「いつまでにガラスを填め込む」という順序どおり設計書どおりに積み上げて完成させていく。しかし、創造的なエンジニアは大聖堂の根幹である「壁画」と「ステンドグラスの装飾」を施していくことが仕事である。計画の途中に、クライアント(発注者)から「どういった聖堂ができあがるのですか?」と聞かれても、「完成しないとわかりません。」としか答えられず、しかも完成予想図とはおよそ異なるものを納品するのがアーティスト(あるいは、クリエイター)の常である。この聖堂の価値は、その建物の規模や建築手法以上に、それらアーティストの圧倒的想像力で決まるのである。
AI時代に生きる我々は、データを利活用することやAIを開発することがこれからの時代に絶対的に必要だと諭され続け、いつの間にか空気のように当然であるかのような感覚になっている。つまり、我々は洗脳されつつあるともいえる。
ならば洗脳されている我々にとっては理由はどうでも良い。自分たちがどのように企業体質を変化させたのかもどうでも良い。我々はもはや疑うことはないのである。そうすると企業のなかで厄介なことが起きる。そもそも誰がやるのか?という問題である。社内のITエンジニアは、従来の立派なITエンジニアである。彼らは、設計書どおりに寸分違わず作り、納期は絶対に守る。それなのに、それでも発注者は自分たちの想像力を超えたものを自然と、知らず知らずのうちに彼らに求めてしまっているのに気づかない。
発注者の求めているモノが変わっても、コトによってはITエンジニアはそうは変われない。いきなり立派な絵画を描けと言われても、描ける人は少ない。ましてや、何を求められているかをスケッチできる発注者はほぼいない。これでは何も始まらないのである。これが企業でいま起きている人材育成の大きな現実である。
(2023年11月14日 HRカンファレンスにおける講演にて)
この記事をシェアする