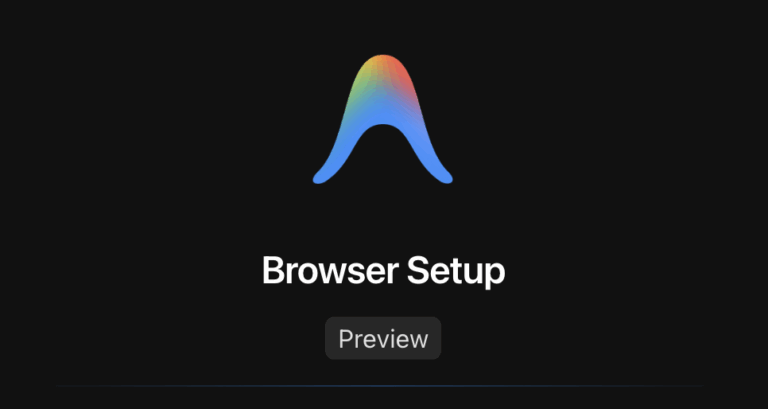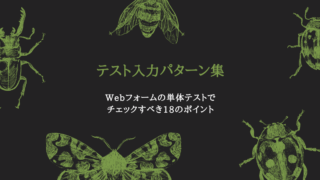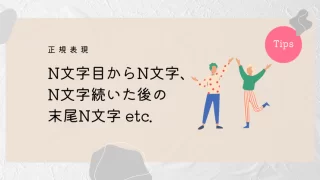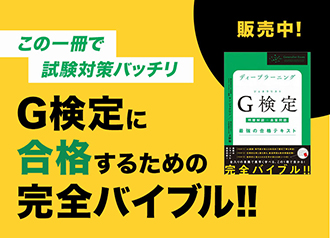ぐっもーにん!yokochanです!
若手社員で議事録マシーンから卒業し、ミーティングのときにお客さんの前で話す機会が増えてきたあなた!
まだお客さんの前で話したことがないけど、これから話す機会が増えそうな新人のあなた!
いまだにミーティングで緊張してミスってしまうあなた!
まずは難しいことを考えずにできることからやってみよう!ということで誰でもできるけど誰も教えてくれないミーティングをうまくこなすコツをご紹介します。
今回は応用編ということでミーティング中の心構えが中心です。
ミーティング前にできることをまとめた基礎編はこちらの記事をご覧ください。

※個人の感覚です。
1. みんな想像以上に覚えていないし忘れている
この考え方は頭に置いておいた方が良いです。
「前のミーティングで共有したから説明しなくても大丈夫っしょ」と思っていると、意外と誰もついていけないまま話が進んでいくことがあります。
そうなると、聞いている人は思い出すことに思考を持っていかれてあなたの話は耳に入らなくなります。
そしてまた次のミーティングでちゃんと聞いていない話の続きになり、理解できないので話が耳に入らず、、というように悪循環になります。
この対策は非常に簡単で、前回のミーティングの内容をスライドに1枚入れておいたり、説明に入る前にこれまでの流れを一言付け加えたりするだけで、「あ~あの話のことね」と理解できあなたの話に耳を傾けてくれるようになります。
特に全体の目的など抽象的な内容は忘れられがちで話に出ないと違った解釈をされがちなので、毎回のミーティングの始めに全体の目的を必ず伝える、といった工夫をするとミーティングの質が上がり、プロジェクトも円滑に進められるでしょう。
2. 一方的に話しすぎない
よくやりがちなのは、自分の伝えたい内容を話すので精一杯で一方的にマシンガントークをしてしまうことです。
区切りの良いところで立ち止まり、質問がないか取り残されていないか確認し、相手と対話することを心がけると良いでしょう。
具体的なやり方として、聞いている人を誰か指名して「〇〇さん質問ありますか?」などと投げかけることは有効だと思います。
指名して質問すると、理解してほしい相手にきちんと伝わっているか確かめることができますし、周りのぼーっと聞いている人も「もしかしたら次は自分に聞かれるかも」と思い、集中させる効果も期待できます。
ただ、これはミーティングの流れを止めないようにしなければいけないので適度に入れることが重要です。
あまりにも細かく止めすぎるとテンポが悪くなるし、質問する相手の見極めを間違えるとあらぬ方向に話が脱線してしまうこともあります。
3. 伝える内容をシンプルにして余力を残して話す
これは少し難しい話だと思います。
自分の今知っているすべてを話すと、想定外の質問をされたときに何も答えられずにあたふたしてしまうことがあるでしょう。
そうならないために、あえて言わないけど質問されたら答えられるという幅をできるだけ多く用意しておくと良いという話です。
初めは伝える内容を考えるので精一杯だと思いますが、一度客観的に自分の話す内容を考えてみると意外と無駄なところが多いはずです。
もっと言うと、必要な話は足りなくて無駄な話が多いはずです。
知っていることがあれば伝えたくなってしまうのが人間の性だと思うので仕方ないです。
無駄とは言いましたが、完全に要らない情報というわけではなく、大半は補足情報としては役立つものだと思います。この補足情報を”余力”として残すことで慌てず落ち着いて話すことができる助けとなります。
なので、まずは削りに削って結論までのシンプルな道筋を作って伝える。
その後に補足情報を付け加える。
この流れが作れるように心がけましょう。
おそらく最初に一人で話を削ろうとすると判断を見誤る可能性が高いので、基礎編でも書いていますが、上司や先輩にチェックしてもらいながら仕上げていきましょう。
4. 雑談を話せるようにする
3つ目の余力に近い話ですが、雑談を話せるということは余裕があるという証拠です。
雑談とは言っても、近所の野良猫の話をしろと言っているわけではありません。
日頃からミーティングで出てくる話題の周辺に関する情報収集を行い、画面がなかなか切り替わらないときや参加者を待っているとき、質問が出ないときなどスキマの時間に関連する話題を振って場を繋げるようにするということです。
咄嗟にちょうどいい雑談をするのは高度なテクニックかもしれませんが、話のネタがあるという精神状態を保つだけでも十分良い効果があると思います。
まとめ
ミーティング中に大事なことは、
焦らない。焦っていることを相手に悟らせない。
ことかなと思います。
とにかくいかに余裕を生み出すか、余裕がなくても余裕があるように見せる工夫はできないか、を考えておけばあなたのミーティングはワンランク上のものになるでしょう。
ではまた。