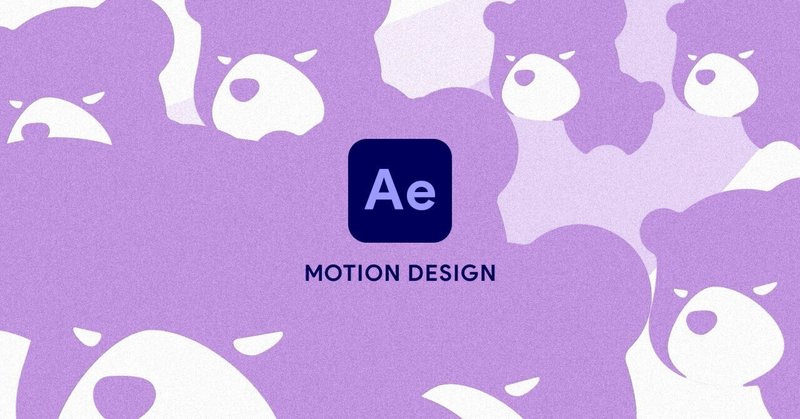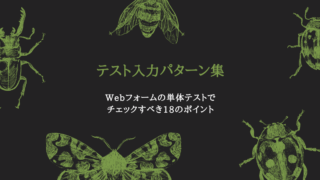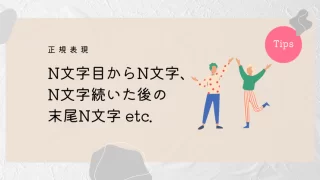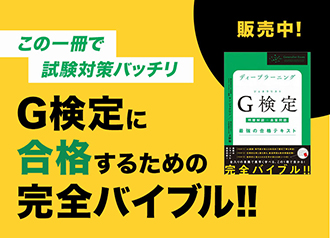こんにちは、プランナーのSALTYです。わたしの専門は企業の新規事業の立ち上げやブランディング、ウェブ等のコンテンツ企画です。
このシリーズでは、「データ」を元に「色調」や「レイアウト」を確定している一般のかたは、あまりなじみがないかもしれない領域をご紹介していきます。
「ウェブアクセシビリティ」の義務化!?
先日、訪問した企業のご担当者さまから伺いました。「今年からウェブアクセシビリティが義務化されたと聞いたんだけど、うちのサイト大丈夫か調べてくれないかな?」と。
間違いではありませんが、実際には、以下の法改正の話題だったようです。2024年4月に「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が改正されました。この法案は、2016年4月に施工されたものですが、改めて今年、義務化と改正が加わりました。ウェブサイトの場合ではJIS X 8341-3:2016に準拠したウェブサイトを作り、ウェブアクセシビリティを確保することがこれに当たります。これをWEB開発会社が「ウェブアクセシビリティが義務化になった」と称して、リニューアルなどをもちかけたようです。現在、法律で義務化にはなりましたが不履行であっても罰則はありません。しかし、企業である限り、お客様や社員に対して、情報到達の点で、視覚的に平等な環境を提供することは企業ブランディング上でも必須事項だといます。
ちなみに、JIS X 8341は「や」「さ」「し」「い」を組み合わせた番号です。
▼事例


↑色調や文字のサイズ、などがJR、私鉄すべてにおいて現在、改善されています。みなさまも身近にも、日常で、公共施設のトイレなどのサインもより大きく、わかりやすく差し替えが進んでいることなどにお気づきになっているかと思います。
ユニバーサルデザイン
上記、法律改正の話しは、日本国内における動きについてですが、デザイン業界では「ユニバーサルデザイン」として1960年代からグローバルには「年齢や身体能力に関係なく、すべての人々が平等にアクセスできる社会の実現」を目指して、建築業界からWEBサイトへと提唱されてきた分野です。当時は、公共の施設やサービスでは、車椅子利用者のためのスロープやエレベーター、視覚障害者のための点字案内板などがなかった時代です。バリアフリーなども進み、現在では公共の施設ではバリアフリーはもちろん、上記事例の交通系のサインボードのように視認性などの点で改善が進んできました。
WEB、スマホアプリ業界では、1990年代から「UI/UX」ということで、カラーコントラストや無駄な改行を加えない、画像にはaltを必須とするなど、レスポンシブ対応、音声再生に配慮することは一貫して基本項目とされてきました。AI化が加速する社会変化が起こる現在、デザイナー等の専門家が介在しなくなる分野では、弱視や色弱、高齢の利用者に情報が正確に伝わるよう視覚・視認に考慮する「ウェブアクセシビリティ」を見直す動きは、重要な事項だといえます。
▼ユニバーサルデザインの歴史
1960年代、建築家ロナルド・メイスが、全ての人々が利用できるデザインの必要性を提唱
1970年代、障害者運動が活発化、公共施設のバリアフリー化が加速
1980年代、アメリカで障害者法(ADA)が制定される
1990年代以降、ユニバーサルデザインは国際的な動きとなる(教育、情報通信、交通などで重要視され改善が進む)
新紙幣もユニバーサルデザイン
漢数字だった一番大きな数字が、ブロック書体のフォントをつかった「数字」に刷新されています。さらに、おそらく見間違えを防止するためではないかと思うのですが「1」という数字については、千円札と一万円札で異なるフォントを起用しています。他にも色調や文字サイズなどさまざまな改善が施されています。ぜひお手元の新紙幣をじっくり観察してみてください。
身近な課題_色覚や利き手
国内の先天色覚異常(1型色覚・2型色覚)については、以下の統計データが総務省調べで出されている数値ですが、
・先天色覚異常は遺伝的要因によって発現しますが日本における発現頻度は、男性
4.50%、女性 0.156%と、グローバルな数値と比較しても多く発現するとされています。
この統計値を用いると、先天色覚異常者は全国に約 290 万人、遺伝的保因者は全国に約 580 万人と推定することができ、 男性の約5%(20人に1人)、女性の約0.2%(500人に1人、保因者(※)は約10%)となります。高齢化も進む中、ますます増加傾向といえ、改めていま日本国内でアクセシビリティの義務化が強く発信されている理由もここにあると思います。
国内の利き手については、右利きが88.5%、左利きが9.5%、両利きが2.1%。イギリス・フランス・アメリカなどにおいては、人口の4-6%が左利きであるといわれている。(クラーク博士:イギリス)など、利き手の出現率は、グローバルとの比較でもこの数値は同じ程度の比率です。
10%程度だとしても、プロダクト等のデザインにおいて、両利きや左利きのかたでも使いやすい工夫を施すことは欠かせません。
あらゆる人に平等なデザイン
以上のとおり、新紙幣、公共施設におけるサインボード、あらゆるシーンでデザインの裏側には、このような法律や基準、配慮が加えられています。今後、利用する立場からも、この観点でデザインに注目していただけたらと思います。
最後にWEBのガイドラインを記載しておきます。お役立てください。
・Web Content Accessibility Guidelines:Webコンテンツをよりアクセシブルにするためのガイドラインです。World Wide Web Consortium(W3C)が策定したもので、サイトやアプリケーションを含む、Webアクセシビリティに関する国際的な基準となっています。