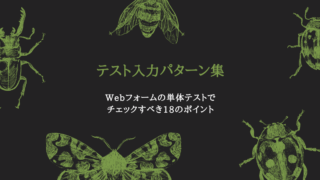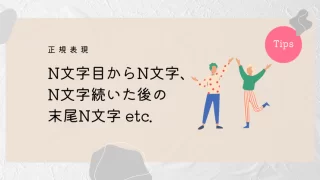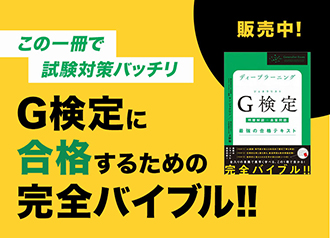「ポオォォォォォォォォォチ!」
その声は、昼下がりの田園風景を切り裂き、青霞む奥羽山脈に跳ね返り、砕け落ちた。
「ポオォォォォォォォォォチ!」
二度目の絶叫を合図に、高松君は、写生用の画用紙と絵具を放り投げ、急斜面の原っぱを全速力で駆け降りる。
しかし、石につまずき、ぐるぐるぐるぐる転げまわると、溝にはまって、その勢いで三転倒立した瞬間翻り、右斜めにバウンドして地べたに落ちた。
「ポオォォォォォォォォォチ!」
高松君の目線の先には、野良犬軍団。
奥羽山脈を背に疾走する美しき直線。

その野良犬軍団の先頭にたち、地平線を切り裂き疾走する白いスピッツは、まさに、その日から1年前に“疾走”ならぬ“失踪”した高松君の飼い犬「高松ポチ」であった。
「高松ポチ」それは、高松君が犬嫌いの両親を説得し続けてやっと手に入れた犬である。
子犬のころは、綿菓子のようにふわふわで笑っているような顔をした愛くるしい犬だった。
高松君は、よく自転車の前かごに、ポチを入れて僕の家にも遊びに来た。
しかし、いつしか高松君を夢中にするものはポチよりファミコンになっていた。
いや、あのころ僕らはファミコン病にとりつかれていたのだ。
スターソルジャーの1秒間に16連射にとりつかれていたのだ。
そう、高橋名人が、何よりも絶対的存在だった。
いつしか、ポチもオトナ犬になり、白い毛は茶色く薄汚れていた。
毎日の日課だった散歩も、数が減っていった。
高松君の家にいくと、ポチがアクロバチックダンスで「散歩連れてって」という。
高松君は、「あのダンスすると、チンチンむき出すから気持ち悪い」とつぶやき、ポチを無視するようになっていった。
そんなある日、ポチが突然いなくなったのである。
鎖を引きちぎり失踪したのだった。
「大切なものは、いなくなってから気づくもの。」と上着を全部ズボンにしまいこむファッションのモッコリ教師が言っていたが、まさか自分たちが思い知らされるとは思わなかった。
「ポチ、どこいった。ポチ、戻ってきて…」
高松君は、喪失感から円形脱毛症になっていた。
それから僕らはポチ大捜索を始めたが、手がかりを掴むことはなかった。
「保健所に連れて行かれたんじゃないか?」という悪いうわさも流れた。
そんな折、隣町で白いスピッツを見かけたという情報があり、追い詰められた僕らは、暴挙にでた。
隣町に偵察にいった僕らの目の前には、白いスピッツがいた。
しかし、まったく顔が違った。
しかも、そのスピッツは僕らを見るなりキバ剥き出しで吠えかかってきた。
さらに、きちんと「ジョンの家」というスプレーで殴り書きされた犬小屋もあった。
僕は、「高松君、帰ろう」と促すと、完全に瞳孔が開いた高松君は
「いや、ポチかもしんね!」
といって、僕らの制止を振り切り、飼い主の門をたたき推定70歳のおばあさんに、
「あのスピッツ、僕の犬っぽいんですけど返してもらえますか?」
と言い放ち、
「お前、バカか?」
と言われ、泣き出すという事件を起こした。
それからもしばらく捜索は続けられたが、ポチが見つかることはなかった。
「ポオォォォォォォォォォチ!」
もはや転げ落ちて泥だらけで草だらけの高松君が最後の声を振り絞った。
そのときである、
野良犬軍団が止まった。
片足をあげたまま、先頭に立つボスである白いスピッツがこっちを振り返った。
「ポオォォォォォォォォォチ!」
「ポオォォォォォォォォォチ!」
「ポオォォォォォォォォォチ!だよな?ポチ、帰ってきてくれたんだよな?」
白いスピッツは、片足をあげたままだ。
「ポオォォォォォォォォォチ!帰ってこおおおおい!」
今までの事情を知る、クラスみんなも叫んだ。
「ポオォォォォォォォォォチ!帰ってこおおおおい!」
クラスみんなで想いをのせる。
「ありがとう、みんな」
高松君は、涙と泥でくしゃくしゃになっていた。
「ポオォォォォォォォォォチ!帰ってこおおおおい!」
「ウォオオオオオン!」
白いスピッツは、それに呼応するかのように、大きな、大きな遠吠えを1つ放った。
しかし、白いスピッツは、いや、高松ポチには既に野良犬軍団という新しい家族があったのだ。
「ウォオオオオオン!」
もう1つ大きく、まるで軍団を鼓舞するように、嘶くと、タッタッタッタッと少しずつ助走をあげ、奥羽山脈の青霞みの中へ走り出す。
そのスピードはひたすらひたすら加速し続け、グングングングンと疾走、そしていつしか地平線の彼方へと消えていった。
「ポス…」
もはや、高松君は、ポチとも呼べないぐらい力尽きていた。
あの、野良犬軍団のボスは、果たして本当に高松ポチだったのだろうか?
いや、そんなことはどうでもいい。
ただ、はっきりわかったのは、僕も、高松君も1つ大人になったということ。
「大切なものは、いなくなってから気づくもの」
それを、高松ポチは教えてくれた。